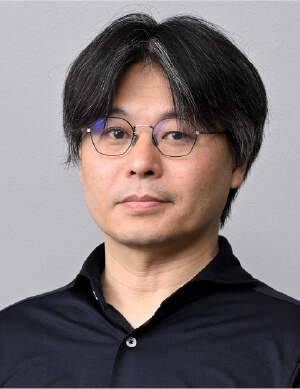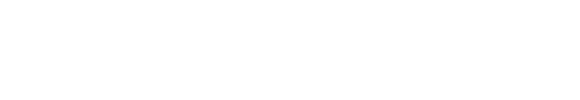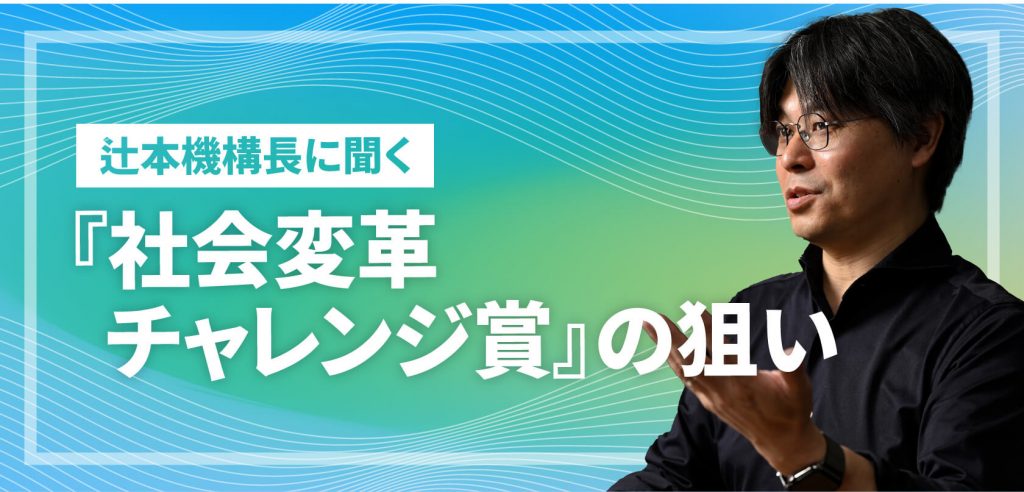
東工大イノベーションデザイン機構(Id機構)が中心となって2024年に創設した『社会変革チャレンジ賞』。なぜ今、大学で社会実装に向けた取り組みが必要とされるのでしょうか。辻本将晴機構長に設立の目的や受賞者への期待、今後の展望などについてインタビューしました。
設立に至るまで、どのような背景がありましたか。
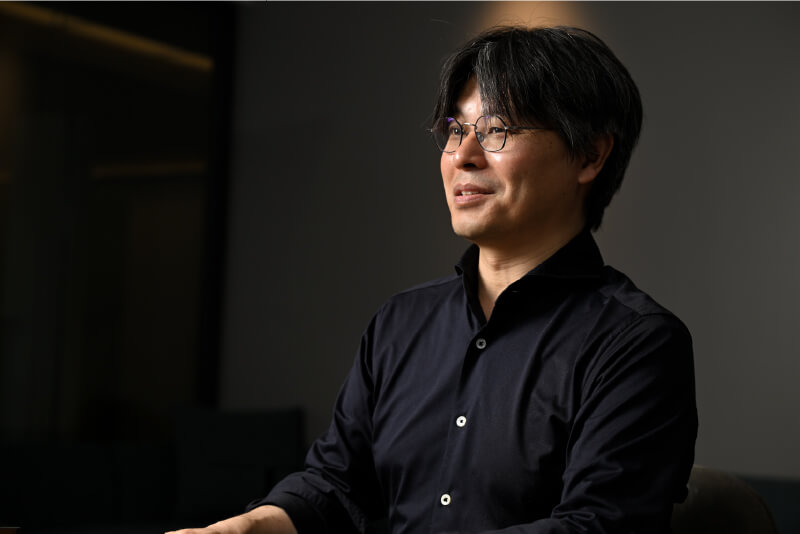
東工大の若手研究者に対して、社会実装の可能性を知ってもらう機会を提供したいと考えたのが発端です。社会変革チャレンジ賞は、Id機構メンバー、特にURA(リサーチ・アドミニストレーター)チームが先導して一緒にディスカッションしながら設立しました。
この賞の目的は、大学の持つポテンシャルを引き出し、優れた研究成果を世の中に還元することです。国が大学発スタートアップ創出を推進し、東工大も2021年をスタートアップ元年に定めるなど、ここ数年は社会実装への追い風が吹いています。ただし起業はあくまで一つの有効な手段に過ぎません。最も重要なのは、「自らの研究で社会を変えていきたい」というマインドセットです。この取り組みによって社会とプロアクティブに関わり、新たな道を開拓してほしいと思います。
表彰式・イベントを通じての感想をお聞かせください。

今回は多数の応募の中から最終的に優秀賞5件、奨励賞10件の計15件を採択しました。これはぜひお伝えしたいのですが、どの研究内容もほとんどクオリティに差はなく、選出には非常に頭を悩ませました。その中から、より社会実装への距離が近い研究を採択した形です。
社会変革チャレンジ賞のリリースを発表して以降、数多くの反響をいただき、我々も手応えを感じています。ここまで多くの若手研究者が社会的なインパクトを念頭に置いている――その事実が浮き彫りになっただけでも大きな成果です。こうしたアクションや強い思いが、企業やベンチャーキャピタルなどのステークホルダーに伝播していけば、米国のようなエコシステムが形成されるのではないかと期待しています。
若手研究者の起業を後押ししていくために、今後どのような支援をされていきたいとお考えですか。
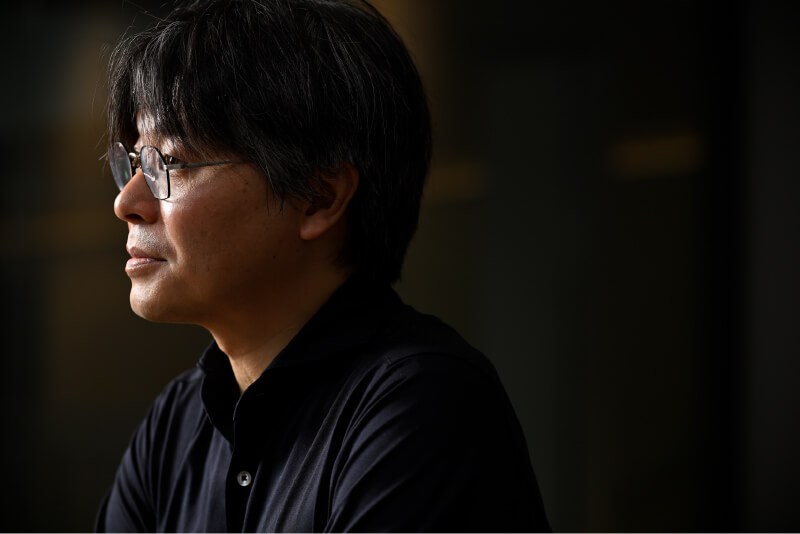
まずは社会実装に向けて研究開発を進めていただくことが第一です。そのうえで我々は背後からしっかりとサポートしていきます。社会変革チャレンジ賞の特徴として、外部からプロフェッショナルのメンターたちを招聘した点が挙げられます。ですから先生たちには“最先端の技術”を存分にプロに伝えてほしい。外部の視点を交えることで突破口が見えてくるチャンスが広がり、何より実務面では強力なパートナーになります。
もともと東工大は、新産業を興す人材育成をテーマに掲げてスタートしました。つまり設立当初から“新しい産業をつくる”DNAが宿っているのです。これまでは、個別の問合せ毎に対応してきましたが、今回のプロジェクトのように組織的に動くことで、この“新産業創造”にむけて大きく前進できると考えております。
最後に、今後「社会変革チャレンジ賞」に挑戦したい研究者、学生たちへのメッセージをいただけますか。
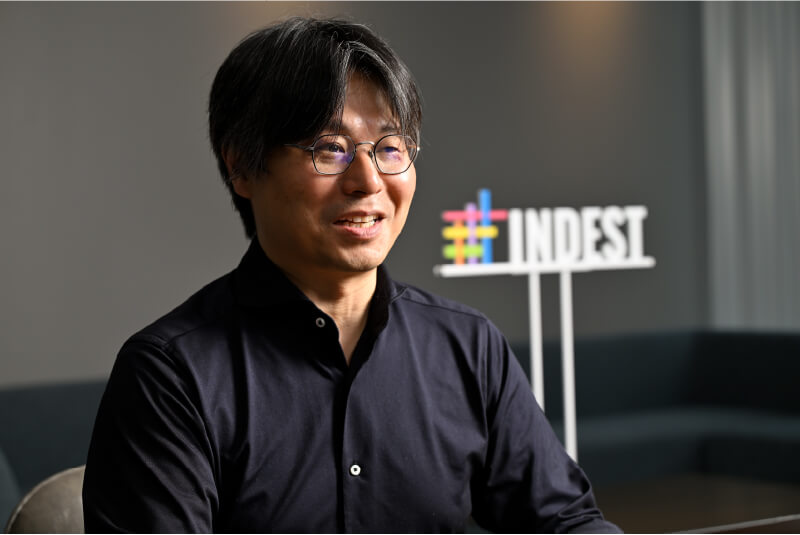
未来の社会に向けて良い影響を与えられるのであれば、研究者のモチベーションは上がります。志を抱く若い先生が増えれば増えるほど、社会実装を実現する力が発揮されます。それにより大学の持つ価値がさらに高まり、産学連携の良好なエコシステムが定着していくはずです。
受賞した先生たちは良い意味で注目を集める立場にあります。研究者の卵である学生たちにとっても大いに励みになりますし、全学を通じて柔軟性や視野の広さを示すことにもつながります。だからこそ自分たちの技術で社会が変わることを信じて、どんどん挑んでもらいたいですね。
研究・産学連携本部・副本部長(起業活動支援担当)
イノベーションデザイン機構 機構長
環境・社会理工学院 教授