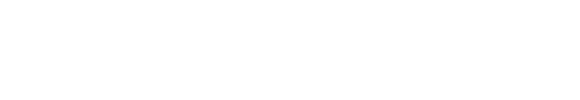東京科学大学の若手研究者を対象に、「研究成果で社会を変えたい意欲をもつ若手研究者」の志を称えるコンテストとして始まった『社会変革チャレンジ賞』。優れた研究に光を当て、2024年7月から事業化に向けたステップを包括的にサポートしてきました。2025年3月5日(水)、東京科学大学 田町キャンパスINDESTで開催された最終報告会の様子をレポートします。
機構長挨拶
〜専門家を巻き込み、社会実装の幅を広げてほしい〜
最初に、本学 イノベーションデザイン機構 辻本機構長が挨拶。現在は米国ボストンのMITで共同研究中のため、ビデオメッセージを寄せました。
「若手の先生たちにたくさんの興味を示していただき、我々としても非常に嬉しかったです。この8カ月間でスタートアップという選択肢に向き合ったことは大きな糧になったと思います。事業化にあたっては自分ひとりですべてをこなす必要はなく、リスクをコントロールできないわけでもありません。なぜならスタートアップに関する知見は十分に蓄積されてきていますし、その道に詳しい人たちは世界中にいるからです。今回のプロジェクトのようにプロフェッショナルとチームを組んで人的ネットワークを築くことで、自らの研究を社会実装する幅が広がるはずです」(辻本機構長)
ファイナルプレゼンテーション
〜12名の採択者が熱のこもったピッチを披露〜
最終報告会では12名がファイナルプレゼンを行ないました。以下、「社会変革チャレンジ賞を通じて獲得できたこと」について、コメントを紹介します。なお三浦智先生、本田雄士先生は『Tokyo Tech Gap Fund Program』2024に採択され、次のステップに進みました。誠におめでとうございます。

総合研究院
山田哲也助教
「低温環境下における固体酸化物形燃料電池と
リチウムイオン電池の共生」
この8カ月間はとにかく忙しかったです。しかし、メンターや関係者と一緒になって計画を立てるステップは非常に充実していました。研究者とはだいぶ異なる視点があり、ときには意見の相違もありましたが、事業内容は確実に進化したと思います。大型GAPファンドへの挑戦など、中身のある楽しい時間を過ごすことができました。
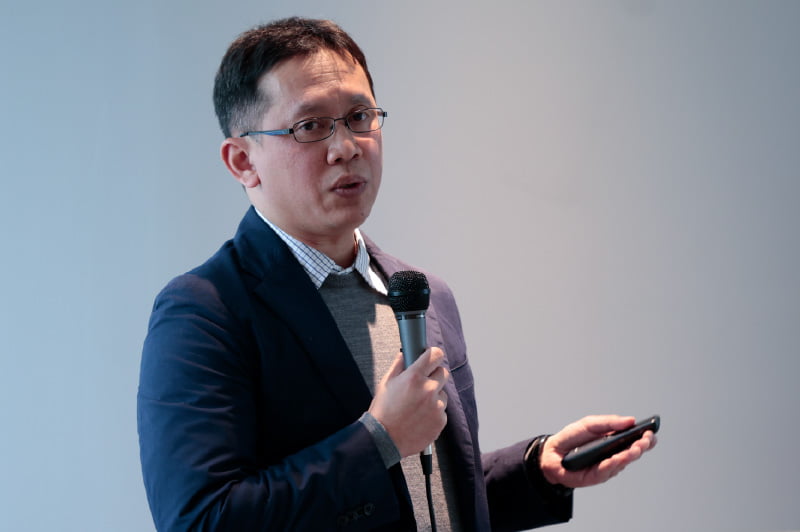
物質理工学院応用化学系
Ambara Rachmat Pradipta
(アンバラ ラクマット プラディプタ)助教
「内在性アクロレインを標的とした革新的がん診断法」
こういうプロジェクトは私にとっても初めてでした。すべてがゼロから手取り足取りメンターの岩崎様に教えていただきました。市場をマクロと捉え、課題はどこにあって、本技術がどう役立つのかという整理をしながら、パートナーを探す機会を得ることの重要性を経験しました。ここからGAPファンドへの挑戦に向かっていければと思います。ありがとうございました。

総合研究院
奥山浩人助教
「迅速性と高感度を両立する膜型バイオセンサー」
これまで研究側の視点しかなかったので、実際にメンターやアドバイザーのアドバイスを聞く中で「そういう見方があるのか」という気づきがたくさんありました。市場の動向だったり、需要と供給の観点から考えなくてはいけなかったりなどです。その点は課題として残っていますが、今後は医療機関、医療関係者と密にコンタクトを取っていきたいと思います。
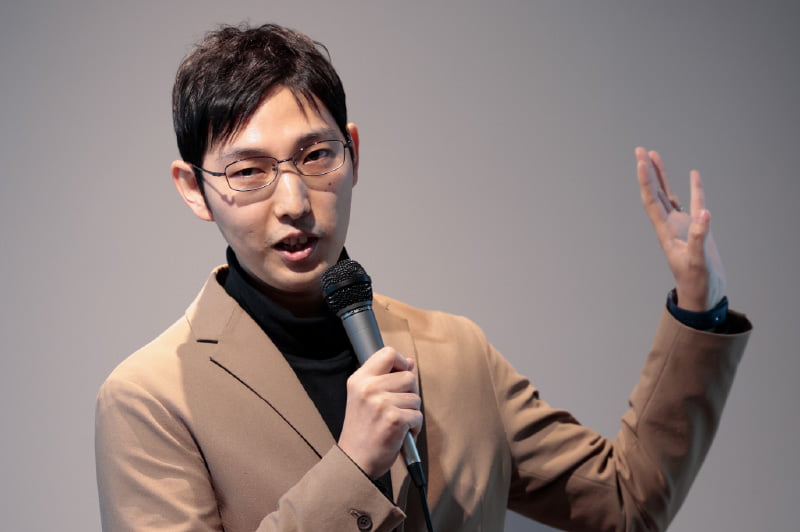
理学院物理学系
森竹勇斗助教
「ジョーンズ行列光バイオセンサの実証と高感度化」
私は物理の基礎研究を専門にしているため、シーズ型の思考すらありません。そんな人間が“市場が求めるニーズ”を考える作業は想像以上に大変でした。一方で、明らかに自分のコンフォートゾーンを飛び出している感覚があったのも事実。得てして人間はコンフォートゾーンを飛び出してこそ成長すると思うので、今回はとても良い機会になりました。

物質理工学院材料系
山口晃テニュアトラック助教
「水熱電気化学による二酸化炭素の
高級炭素化合物への変換」
私が本プロジェクトを通じて獲得したことは、1.関連分野における事業の現状把握、2.研究とビジネスにおける着眼点の違いの認識、3.事業化に向けた優位性の具体的な説明法の3点です。
1.に関しては自分の研究がどのような事業に結びつき、どのような可能性があるのかについて考える機会となりました。2.に関しては研究において重要だと思っていることがビジネスでは必ずしもそうではなく、その逆もまた然りということを改めて認識しました。3.に関しては競合と比較して経済的あるいは実質的優位性について学ぶことができました。

総合研究院
朱博(シュ ハク)助教
「薬物放出制御のための
スイッチ型抗体薬物複合体の創出」
本プロジェクトでは、メンターの方々と毎月のようにミーティングを重ねました。明確なマイルストーンを立て、競合調査の実施から実用化に向けて、研究開発のためにどのような努力をすればいいのか、さらには、ビジネス化を見据えたディスカッションから、どれだけシンプルに自分の技術を説明するのかについてさまざまなアドバイスをいただきました。
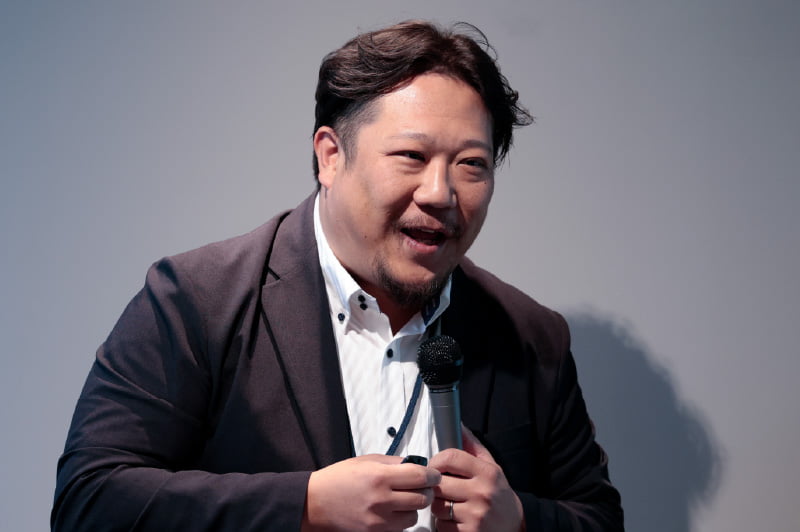
総合研究院
安井伸太郎准教授
「環境循環型低コスト全固体電池」
2週に1度のメンタリングで、重々ご指導いただきました。課された宿題をこなす中、SU立ち上げに関する考え方が構築できたこと、中でも、エネルギー市場を熟知した経営者候補がこのプログラムをきっかけに参画したことです。事業構想が一息に進み政府関係者、材料系事業有識者、電池業界のキーマン、製造パートナーとの対話もトントン拍子に進み創業も間近になっております。何よりも社会変革チャレンジ賞の8カ月間の活動を通じて得られたものは“人のつながり”。URAの支援スタッフを通じていろんな方々と話をさせていただき、自分の培ってきた技術を世に出す手ごたえを感じてます。

物質理工学院
木村健太郎助教
「低温CO2水素化・FT合成を可能とするCuMgFe型
ハイドロタルサイトを基盤とした高機能触媒の開発」
ビジネス化に向けてはざっくりとしか理解していませんでした。しかし、プロジェクトを通じて想定よりも多くの需要があることがわかり、実現すれば大きなビジネスになる手応えを感じました。もう1つ、私の技術で欠かせない水素は再生可能資源ですが、高いコストが発生します。そのコストの問題を見直し、研究の枠組みを再構築できたと思います。

総合研究院
李尚曄(イ サンヨプ)助教
「パターン印刷による低コスト・広帯域電波部材の開発」
基本的にアカデミックの人間なのでビジネス戦略には興味がありませんでしたが、メンターやアドバイザーとのミーティングを通じて視野を広げることができました。その結果、社会変革チャレンジ賞の予算で3件の特許を登録。2025年2月12日には「株式会社M2T2(エムトゥ―ティートゥー)」を設立し、未来への架け橋として運営していきます。このことが8カ月間で最も大きな出来事になりました。

物質理工学院
山本雅納助教
「多孔性グラフェン材料製造の技術実証」
事業化に向け、自動車メーカーの電池開発チーム、炭素製品メーカー、非鉄金属メーカーなど企業の専門家からヒアリングすることができました。特に本プロジェクトで競合となる炭素メーカーの方からは多大なアドバイスをいただき、ともにディスカッションするなど貴重な経験をさせていただきました。また、メンターの指導のもとで、グローバルでの炭素材市場調査や先行する特許のスクリーニングを実施したことで現在地点がクリアになりました。調査で得た情報をベースに改めて開発戦略を策定。アカデミアとの共同研究を進めるとともに、すでに企業からも開発支援をいただいています。何より、本プロジェクトを通じて事業化の解像度が向上しました。メンターやフォロワーの方々、そして本チャレンジを後押し頂いたイノベーションデザイン機構 (Id機構) の皆様に心から感謝申し上げます。

総合研究院
菅原勇貴助教
「化学産業のパラダイムシフトをもたらす
革新的電気化学触媒の創出」
この8カ月間で、いろんな大学や企業の方々と会って情報交換を行ない、私が研究している技術の長所、短所を整理することができました。また、市場調査を実施して今後の事業化に向けたニーズ、既存の技術に対する革新性・優位性を確認し、顧客の姿を整理しました。これまで基礎研究しかしてこなかったので今回のような取り組みは初めてでしたが、非常に勉強になりました。

総合研究院
三浦一輝助教
「光による疾患治療を実現する
分子標的型光線力学療法」
2025年3月3日に大学経由で特許出願を行いました。そのことが私にとって最も大きな収穫です。また、基礎研究の世界から事業化について考える初めての経験は、とても勉強になる8カ月間で、メンターの指導を受け、市場のニーズを踏まえたうえで創薬シーズをどのように社会展開すべきかを学ぶことができました。

環境・社会理工学院
Cheng Shuo(テイ シャク)助教
「磁場アシストフロー電極を用いた
微生物燃料電池の開発」
※2025年3月5日(水)の最終報告会はご欠席のため、コメント掲載は割愛させて頂きます。
表彰・総括
〜第一期生として、大きく成長することに期待〜
ファイナルプレゼン後には、メンター、アドバイザーの投票によって選ばれた「最優秀ゲームチェンジャー賞」「優秀ゲームチェンジャー賞」各1名の表彰が行なわれました。最優秀ゲームチェンジャー賞は安井先生、優秀ゲームチェンジャー賞は山本先生が受賞。奇しくも2人とも電池関係の研究者であり、メンター代表の川上登福様(株式会社先端技術共創機構 代表取締役社長)は、「シーズとニーズのギャップを埋めて、どのようにビジネスにつなげていくかが大切。さらに充電を図って頑張ってください」とのエールを送りました。

優秀ゲームチェンジャー賞を受賞された山本先生(左)
最後に東京科学大学の波多野睦子理事・副学長(研究・産学官連携担当)が、「社会変革チャレンジ賞は、自らの研究で社会を変える第一歩。皆さんには第一期生として、今後も新たな道を開拓してほしい。今回のチャレンジを糧に、大きく成長することを期待しています」と総括しました。
東京科学大学のミッションは「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」ことです。大学発のディープテックスタートアップは、世界を変える産業創出であり、社会課題を解決する手段でもあります。イノベーションデザイン機構では、これからも若手研究者の挑戦を支援していきます。