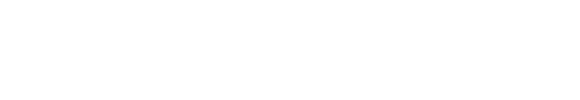イベント・ニュース EVENT / NEWS
2025年7月4日
【開催報告】Science Tokyo Startup Night2025②
日時2025年 6月26日(木)16:00-21:00
東京科学大学イノベーションデザイン機構は、2024年6月26日(木)虎ノ門ヒルズCIC Tokyoで、Venture Café Tokyoとの共催イベント「Science Tokyo Startup Night2025 」を開催しました。こちらは、開催レポート第二弾です!
目次
Science Tokyo Startup Night2025①|オープニング/基調講演/ディープテック女性起業家セッション
Science Tokyo Startup Night2025②|インタビューセッション/オープンディスカッション/閉会
Science Tokyo Startup Night2025③|社会変革チャレンジ賞2025授賞式
⑥18:25 – 18:45
インタビューセッション
最高の成果を生む、起業と投資のエコシスムー世界を動かす才能、日本の大学への期待
本セッションには、シリコンバレーのトップベンチャーキャピタル・SOZO Ventures 創業者の中村幸一郎氏をお招きし、日本のスタートアップが世界で戦うために必要なエコシステムのあり方についてお話しいただきました。インタビュアーは、本学イノベーションデザイン機構 機構長の辻本将晴教授。ここでは、スタートアップの国際展開、ディープテックの定義、大学の役割に至るまで、実践的かつ洞察に満ちた対話が繰り広げられました。
課題は「制度設計」と「グローバル資金」
中村氏は、Twitter、Square、Coinbase、Zoom、Palantirなど、名だたる企業に投資をしてきた SOZO Venturesの共同創業者。シリコンバレーを拠点に、国際展開を迎えるグローバルプラットフォーム企業の日本を中心とした国際展開をサポートして投資をしています。これまで、毎年1−2社世界中で生まれる、時価総額で100ビリオンドル(日本円15兆円)規模に成長する企業を過去10年間で4社投資をしてきています。スタートアップ投資の最前線から、日本のエコシステムにとって重要な幾つかの点の提示がありました。中村氏は、企業価値1000億円を超えるようなスタートアップを生み出す力は20倍以上あると思いますが、そのために大きく変えなくては行けない点の一つが国際協調投資、つまり、海外の成功企業のほとんどがアメリカを中心とした自国以外の海外投資家から投資を受けていることを指摘しました。日本のベンチャーがグローバルに育つには、海外資本を適切に取り込むことが不可欠とし、そのために必要な、法制度や会計、企業評価制度、人材の国際化の必要性を語りました。
「ディープテック」は科学技術ベースの戦略領域
また、セッションの中で、制度設計者が適切なイノベーションに関する適切な専門知識を持つことの必要性についても触れられました。具体例として昨今、注目が集まり様々な支援策が作られている「ディープテック」という言葉についても、改めて明確な定義とその対象に対する効果的な制度設計の重要性の指摘をされました。「実現できれば、世界全体で解決すべき社会課題の解決などが測れる科学技術」と定義される「ディープテック」ですが、どのような技術分野が「ディープテック」にあたるのかが明確にされていないケースも多く、場合によっては大学に関連するありとあらゆるスタートアップがその対象とされている場面も散見されます。他方、アメリカのDARPAやNSF等の学術機関では、何を研究フェーズの科学分野、と技術分野、また、フェーズの違いによる優先度の整理がされています。例えば、分類によると顕在しているニーズと明確になっていない潜在ニーズの座標軸で分け、顕在ニーズの中で社会課題にインパクトを与える分野が「ディープテック」と定義されています。このような定義が明確にされると、どのような分野が「ディープテック」として支援を注力すべきか、また、「ディープテック」に至る前の研究分野の中でも将来の「ディープテック」分野の開発と深く連携するどの分野に注力すべきかという議論が精密に可能になります。どの段階の技術に、どれだけの資金と時間を投じるか—その判断基準を制度設計として明確にしていくことが重要である、と説明しました。
起業は「登山」──大学の果たすべき役割
優れた研究者が1人で起業してもうまくいかない。研究とビジネスの「機能」をそろえたチームを組むことが重要、と説く中村氏は、大学が研究者とビジネス人材を引き合わせる、登山パーティーを編成するような役割を果たすべき、と提起。ビジネス経験者と連携し、急成長の知見を共有する環境を整えることが、世界と戦えるスタートアップを生むカギになるといいます。辻本教授から「どの段階から海外と連携すべきか」と問われると、「最初からグローバルなチームを設計することが不可欠」と応じました。その中で、留学生の存在が重要な要素になると指摘。多様な視点と文化が自然と交差する彼らの存在が、初期から国際基準のチーム形成を後押しするはず、と述べました。
スタートアップは「20年プロジェクト」
最後に中村氏が強調したのは、時間軸のずれでした。成功したスタートアップは成長に10年以上かかっているという現状に触れ、スタートアップの世界では、会社の創業から投資、上場後の安定成長まで平均12〜15年、20年かけて取り組むものだという認識が必要、と語りました。また、スタートアップは数の勝負ではない。10人、20人の本当に優秀な人材を支え、世界を変える1社をつくることが大切である、と述べ「才能を見出し、支え、時間をかけて育てること」。それが、日本の大学に求められる次のエコシステムにつながるものとして結びました。

(SOZO Venturesファウンダー兼マネージングディレクター 中村幸一郎氏/東京科学大学 イノベーションデザイン機構長 辻本将晴)
⑦19:00 – 19:30
Open Discussion
世界を変える大学発ディープテックの成功と失敗を決める創業経営者とは
時価総額1000億円を超えるディープテック企業は、いかにして生まれたのか?
本イベント最後のセッションでは、ディープテックスタートアップの立ち上げと成長の核心に迫り、研究者・経営者・大学、それぞれの視点から「創業経営者に求められる資質」と「大学の役割」について、レジェンドによる議論が交わされました。
最初に登壇したのは、衛星データ活用ベンチャーSynspective創業者の白坂成功氏。国家プロジェクト「ImPACT」で得た技術を社会実装するため、自ら会社を設立しながらも、「自分は経営をしない」とCXO就任を辞退。その代わりにCEOを含む経営チームをゼロから探し、半年の時間をかけて、人間性と資質を備えたパートナーを見つけたといいます。選定における5つの条件(宇宙以外のビジネス経験、宇宙技術への理解、スタートアップ経験、国際性、行政との対話力)は、ディープテックの特性と事業スケールの文脈において強く示唆的なものとなりました。
続いて、日本発ユニコーン「ペプチドリーム」の創業者でもあり、現在はケイエスピーで多くのスタートアップ支援に携わる窪田規一氏は、経営者育成の実践知を展開。「サイエンスを理解する力と経営のセンス、そして何より「やる」という情熱が不可欠」と語る。特に、技術の優位性をオンリーワンとして市場に提案できるマーケティング思考や、顧客の本質的ニーズを読み解く「鏡面対話」の重要性を強調しました。また、ビジネスにおいて文系理系の区分は意味をなさず、分野横断的な好奇心と貪欲さを持つ人物こそが経営者に向いている、と展開しました。
大学からの視点としては、東京科学大学 副学長 渡部俊也教授が登壇。大学発スタートアップにおける創業経営者の選定やマッチング支援の必要性、そして人材ネットワークの構築と活用の課題を指摘した。人材DBだけでは成功確率は上がらず、個別性や相性といった「見立て」が欠かせないことにも触れ、創業支援は「焦らず、個別に、理解を深めながら進めるべきもの」と提起しました。
登壇者全員が共通して口にしたのは、「ディープテックも、商売である」という現実。優れた技術があっても、それを「売る」ことのできる経営者でなければならない。ディープテックという言葉に惑わされず、「ものが売れるか」「チームを組めるか」「世界と戦えるか」という視点が、これからの大学発スタートアップの成功の鍵になる、ということでした。
大学が果たすべきは、技術と経営、研究者とビジネス人材の橋渡しであり、そのために必要な人材観、制度設計、支援の仕組みについて、あらためて多くのヒントや気づきを提与えてくれるセッションとなりました。

(株式会社Synspective 創業者、慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 白坂成功 氏/ペプチドリーム株式会社 創業者・株式会社ケイエスピー 代表取締役 社長 窪田規一氏/東京科学大学 副学長(スタートアップ担当)渡部俊也)
⑧19:50 – 20:00
表彰式/クロージング
本イベントの締めくくりとして行われたのは、研究者ピッチコンテストの表彰式と、東京科学大学 波多野理事によるクロージングリマーク。スタートアップを志す精鋭研究者たちの挑戦をたたえるとともに、本学の研究・起業支援の未来ビジョンが語られました。
研究者ピッチ|受賞者発表
表彰式では、5名の研究者によるピッチの中から2名が受賞者として選出されました。
オーディエンスアワードは、東京科学大学工学院のファム教授が受賞。「超省力・超高速動作を可能にするエッジAI半導体向けの不揮発性メモリ」というテーマで注目を集め、会場投票によって選ばれました。ファム教授は受賞スピーチで「学生に夢を見せるためにも、研究者自身が挑戦する姿勢が重要」と語りました。
また、グランドプライズ(最優秀賞)には、生命理工学院の上野教授が選ばれました。発表テーマは「細胞内生成反応を活用した革新的タンパク質製造プロセスの確立と実証」。すでにGAPファンドの支援や 研究所との連携も進んでおり、基礎研究とスタートアップ活動を両立する姿勢が高く評価されました。
表彰式では、本学 羽多野理事がそれぞれの健闘を称え、「基礎研究とビジネスを分ける時代ではなくなった。いま求められるのは、両者をつなぐ新しい知の在り方である」との言葉が添えました。
クロージング
イベントの最後を飾ったのは、波多野理事によるクロージングリマークです。
理事は「本日のセッションは、最先端テクノロジーと社会課題の交差点で挑む皆さんの熱量に満ちていた」と述べ、登壇者の言葉を引用しながら、次の時代への手応えを語りました。「ディープテックには20年かかる」「日本のエコシステムが音を立てて変わりつつある」といったコメントを引き、東京科学大学が取り組むビジョナリーイニシアティブの可能性に言及。分野を越境する研究戦略のもと、基礎と応用が並走する研究体制を築くこと、そして、医療系との新たな連携や、研究者・起業家・投資家がつながるコミュニティ形成によって、「世界を変える大学発スタートアップ」の創出に向けて着実に歩みを進めていることについて、述べました。おしまいに、「スタートアップに必要なのは、経営者、制度、仲間。今日の出会いが、未来を動かすネットワークの起点になる」とエールを送りました。

(STGF受賞者、波多野睦⼦理事・副学⻑)
本イベントには、多くのみなさまが駆けつけてくださいました。現地参加のみなさまはもちろん、オンラインでご視聴いただいたみなさま、ご登壇のみなさま、関係者のみなさまにも、深くお礼を申し上げます。

東京科学大学は、今後もディープテックの社会実装と、研究者・起業家・支援者がつながるエコシステムの構築に力を注ぎ、”世界を変える”大学発スタートアップの創出をめざして挑戦を続けてまいります。今後とも、変わらぬご支援とご関心を賜りますようお願い申し上げます。
(テキスト・サムネイル URA 小川由美子)