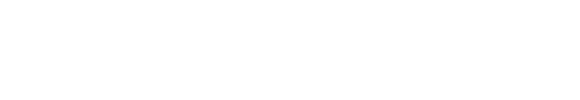イベント・ニュース EVENT / NEWS
2025年3月17日
開催レポート|EIR活動報告会2024
日時2025年 2月27日(木)14:00-17:00
東京科学大学では、認定ベンチャーの経営を担う人材の育成や、起業・成長支援を目的とした取り組みを積極的に進めています。その鍵となる人材が「客員起業家(EIR:Entrepreneur in Residence)」 。客員起業家は、大学の研究成果を実用化し、社会にインパクトを与えるスタートアップを育て、ビジネス化を促進させる人材です。
東京都が実施する、多様な主体によるスタートアップ支援展開事業 | TOKYO SUTEAM採択事業者でもある本学は、研究の社会実装化において、このEIR人材が参加することで、情報収集・分析力を強化し、海外展開を見据えた事業モデルの策定を目指すべく、本年度この事業に取り組んでまいりました。
本イベントでは、2024年度本学で活躍したEIRの活動報告を通して、EIRとして働く魅力やその役割、多彩な活動内容について紹介しました。
EIR活動報告会 2024

開催日: 2025年2月27日(木) 14:00-17:00
会場: INDEST 4階ラウンジ
当日タイムテーブル
・14:00-14:10 ご挨拶|INDEST紹介
・14:10-15:00 東京科学大学EIR(下記5名)からの活動報告紹介
-江上 陸 氏
-落合 章浩 氏
-土橋 匠 氏
-末宗 拓馬 氏
-谷村 勇平 氏(代読)
・15:00-15:45 upto4 棟兼彰一氏(upto4株式会社 代表取締役)による大学EIRの事例紹介
休憩
・16:00-16:30 EIRの活動に関するディスカッション
・16:30-17:00 ネットワーキング|現地参加者のみ
開会挨拶
本イベントは、イノベーションデザイン機構進士副機構長による挨拶で幕を開けました。東京科学大学におけるイノベーションデザイン機構の取組を紹介し、今年度の「TOKYO SUTEAM」事業や今後の本学スタートアップ支援においてEIR人材がいかに必要不可欠であるかを伝えました。
東京科学大学EIRからの活動紹介
今年度本学EIRとして活動した5名が、それぞれの活動ややりがい、今後の参加者へのメッセージなどを発表しました。
1.江上 陸 氏
研究の価値を理解し、社会に大きなインパクトを与えるために、ビジネスパーソンとしての分析力や交渉力を活かしつつ、サイエンスドメインの知識を活用。EIRの想いとして、ディープテックが社会にもたらす価値を研究者と共にデザインしたいと述べ、自由な発想を大切にしながら、技術の具体化を目指して仮説を考え続ける、という姿勢を示しました。
2.落合 章浩 氏
研究シーズの発掘や事業開発に従事する中、緊張感を持った事業推進や新たな出会いの喜びについて語った。フルコミットできないことに対する歯痒さも感じつつも、ディープテックEIRとして先端研究に触れる楽しさや将来へのインパクトを実感し、そこにやりがいを感じていることを強調しました。
3.土橋 匠 氏
EIRとしての活動における難しさとして、技術理解のハードルが高く、ターゲット市場の特定が難しいことを指摘。また、投資家などへのプレゼンテーションの特殊性についても触れ、ビジネススキルの重要性を強調しました。ディープテックスタートアップは技術だけでなく、様々なビジネススキルが求められる“総合芸術”であると述べ、日本には事業化可能な技術シーズが豊富に存在すると期待を寄せました。
4.末宗 拓馬 氏
日本・世界トップレベルの研究テーマに関与できることや、幅広い研究シーズに出会えることが、やりがいだと述べました。技術理解には多くの時間を要し、様々な知識が求められる業務であることを認識しつつも、まずは行動することの重要性を強調。EIRを通じて、画期的な研究成果の社会実装を目指す決意を示しました。
5.谷村 勇平 氏(代読)
日本の大学から価値ある技術が社会に実装される姿を見たい、という想いからEIR活動に参加。理想と現実のギャップについても触れ、スタートアップ創業と大学とのカルチャーギャップを埋める努力の必要性、事業コンセプトと技術シーズをつなぐことの重要性を強調しました。一方でより難易度の高い技術で事業を構想でき、社会価値の高いテーマに挑戦できることのやりがいについても語りました。
大学EIRの事例紹介 (upto4株式会社 代表取締役棟兼彰一氏)
up to 4株式会社(https://www.upto4.com/home)は、研究シーズの社会実装化を目指し、研究開発型スタートアップの創業支援・インキュベーションを強みに、大学や自治体などとEIR募集イベントなどを開催。大学スタートアップの課題解決に取り組んでいます。大学発スタートアップの経済効果に対する期待は大きく、国やプロジェクトも多く存在するものの、「経営者がいない」という問題を指摘。この問題解決の為のEIR人材の重要性を説いて頂くと共に、フルタイム型やパートタイム型など多様なEIR参画パターン、また EIR(CxO候補者)の参画事例について解説しました。最後は「是非EIRに関心を持っていただき、多様なメンバーと協業できる体制を検討してください」と、強い言葉で締めくくりました。
EIRの活動に関するディスカッション
続いてのパネルディスカッションでは、“顧客との接点の取り方”や“本業との兼ね合い”、“望ましい研究者との関係性”など、EIRにおける重要な視点が共有されました。“EIRの適性”としては、シーズを世に出すことへの興味が大前提、技術のポテンシャルを理解し、キャッチアップする力についての声が多くありました。「(現在関わる事業について)将来の経営サイドへの参加意欲は?」という、会場からの質問に対しては、「縁と機会次第だが、やらないと人生後悔する」との、将来CXO候補としてシーズに参加したい、という力強い回答もありました。
まとめ
客員起業家やEIRという言葉が、大学発スタートアップの文脈で、メディアに登場してくるようになった昨今。とはいえ、その実態についてはまだ知られざる部分もあり、生の声にふれる貴重な機会となりました。“先端研究に触れる楽しさと将来に与える社会的インパクト”―。これがEIRの何よりの醍醐味であり、ディープテックの社会的価値を研究者と一緒にデザインしたい、という彼らの強い想いこそが、研究の実装化を加速するという、実感につつまれた会場でした。
東京科学大学は、引き続き大学の研究成果の実装化にむけて、ビジネスを促進させるEIR人材の育成や募集に注力できればと思います。
(テキスト・写真:URA湯原理恵)