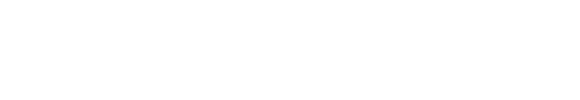Gap Fund 採択者インタビュー
2023年度採択者
2024年8月28日
物質理工学院 伊原 学 教授

世界初のCO2と炭素を使った大容量蓄電システムの実用化
――応募動機について教えてください。
この世界初のカーボン空気二次電池システム‘CASB技術’の研究開発プロジェクトが終了し、次の段階として、期待していた実用化のための大型予算の獲得が上手くいかなかった時期、このGAPファンドのことを知りました。
実用化に向けての「ギャップ」を感じる中、研究フェーズから実用化フェーズへの移行には、技術的なギャップだけでなく、私の場合、資金のギャップと、実用化に向けて何をすべきかの意識のギャップが特に問題でした。その結果、この期間中を通して、データ取得以上に様々な視点で頭を使い、大きな発明が生まれ、次の予算獲得にもつながりました。
Id機構やVCの方々との月1回のミーティングを通じて、研究者としての論文執筆とは別のフェーズについて、意識することが出来るようになり、投資家の視点から見て、何をすれば投資を受けられるかを具体的に考える機会が増えました。結果的に、PCT出願に至るまでJSTの支援を受け、今回の事業化のコアとなる発明ができたことに大変感謝しています。
――1年参加してみてのご感想を教えてください。
プログラムに参加して、技術開発のみに専念するのではなく、事業化に向けた意識の変革がいかに重要であるかを痛感しました。技術的な課題をクリアするための研究はもちろん大切ですが、それ以上に事業化するための視点を養うことが必要だと感じました。特に、投資家やビジネスパートナーとどのように対話し、彼らの視点で物事を捉えるかも鍵となります。
GAPファンドのプログラムを通じて、伴走してくれるId機構や、VCの皆さんから多くのアドバイスをいただきました。研究者としての論文を書くフェーズとは異なる、実用化に向けた優先順位を理解することができました。データ取得よりも頭を使う部分が多く、限られた予算内で、新たなアイデアを生み出すことに集中できたのは非常に有意義でした。意識のギャップが大きいということを再認識し、そのギャップを埋めるためにどのようなアプローチが必要かを学んだように思います。
プログラムを通じて得られた最大の成果の一つは、大型グラント出願まで支援を受けることができたことです。これにより、事業化のコアとなる発明も生まれ、具体的なプロトタイプの製作にもつながりました。さらに、実際に動作するものを見せる、見せるものをつくるというのが最大のアピールになると知り、多くの方々に技術の可能性を納得してもらうことができるようになりました。
研究者は、往々にして、なるべく正確に述べようとするがために、時として説明がわかりにくくなるような部分があります。ですが、ある程度の正確性を省いても大事なことを、キャッチーに伝える事が重要になる時もある、と学べたのは大きな収穫です。このような経験を通じて、今後のプロジェクトの展望について具体的なビジョンを持つことができました。
――今後のプロジェクトの展望についてお聞かせください。
資金調達を考えると、まず、グラントをできるだけ獲得しながら、創業準備を計画しています。会社は作って終わりではなく、その後も重要です。創業後もディープテックのユニコーンを目指し、しっかりと育てていきたいと思います。これから東京科学大学が飛躍していくために、ディープテックによって、産業を立てていくことが重要だと思っています。
創業準備段階では、グラントを取って、私たちが主導権を持って投資を受ける状態まで事業を確立させてくことが必要だと考えています。大型のグラントの採択を獲得することで、スクリーニングを受け、外部評価を受けた証になり、信頼にも繋がります。10年後にはIPOを目指したい。戦略としては、市場を取るために知財戦略をもって、初期市場投入と研究開発を並行して進め、パフォーマンスを向上させるフェーズを作っていくストーリーです。
――新規応募者へのメッセージをお願いします。
今、このギャップファンドを検討している皆さんにメッセージを送ります。基礎的な研究が大好きな方も多いと思いますが、基礎研究は社会に出ることで世界を変革できる技術に育つ可能性があります。
私自身も研究が大好きで、研究を続けたいと思っています。また生まれた技術が社会に出て、さらに社会を豊かにする技術に育つことを常に願っています。以前は、大企業と共同研究を行い、一つのプロダクトとして実現することが現実的なプランだと思っていました。しかし、最近は考えが変わってきています。大学の立場としては、スタートアップを立ち上げ、自分たちが主導権を持って技術を社会に実装することが、最も早い道かもしれないと思うようになりました。
技術があって、それを実用化するためには、さまざまなサポートが必要です。ギャップには技術的なものもありますが、実際には、「意識のギャップ」の方が大きいと感じます。このGAPファンドプログラムの予算額は、他のファンディングに比べて少ないかもしれません。しかし、その分、さまざまな知恵やサポートをしてくれる方々がいますので、ぜひ応募を検討してみてください。これは、新しい東京科学大に向けての大きな力となるはずです。我々が、世界の理工系トップの大学になることを、あなたが実現していく。ぜひ、ご検討いただきたく思います。

伊原 学
物質理工学院 教授