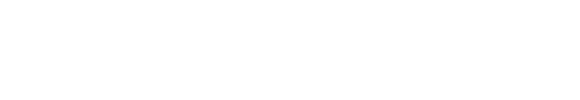イベント・ニュース EVENT / NEWS
2025年5月15日
特別対談|「研究シーズからの事業創出—GAPファンドから始まる大学発スタートアップと大企業の共創モデル」~みらい創造インベストメンツ × 芙蓉総合リースが描く未来~
日時2025年 4月
2025年4月、東京科学大学田町キャンパスINDESTに、株式会社みらい創造インベストメンツと芙蓉総合リース株式会社の代表のお二人を迎えし、それぞれの立場からGAPファンドの役割やディープテックスタートアップとの共創の可能性について、お話を伺いしました。

GAPファンドが果たす役割とその意義
東京科学大学・芙蓉総合リース株式会社(以下、芙蓉リース)・株式会社みらい創造インベストメンツ(以下、みらい創造)は、2017年10月に『新産業の創出・育成のためのギャップファンドの設置および運営に関わる組織的連携協定』締結後、ファンドの公募化や事業化支援メニューの拡充を続け、大学発のイノベーション支援を行っています。
「芙蓉みらいGAPファンドプログラム」は、芙蓉リースが資金を拠出し、みらい創造が東京科学大学の技術の社会実装化にむけて伴走支援することで、3機関が一体となって大学発のイノベーション創出の加速化を目指すプログラムです。
東京科学大学の優れた技術シーズと事業化の間に存在するギャップを埋め、技術シーズの実用化に向けた支援を進めることで、社会変革や社会課題解決に貢献するスタートアップが持続的に創出される体制を構築しています。
GAPファンドがスタートアップにとって「最初の一歩」となる理由
大学発スタートアップにとって、研究成果を社会実装へ進める道のりには、資金的・人的・制度的な障壁が多く存在します。特に、研究開発段階と市場導入の間に存在するいわゆる「死の谷」をいかに越えるかが、起業の成否を左右するともいわれています。そのギャップを埋めるためのファーストステップとして、重要な機能を果たすのがGAPファンドプログラムです。本プログラム開始当初から関わってきた芙蓉リースは、社会課題の解決と、企業価値向上を両立するCSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)の視点からこの取り組みに共鳴し、みらい創造と共に制度設計から深く関与してきました。
― GAPファンドがスタートアップにとって「最初の一歩」となる理由は何でしょうか
下條氏「研究者にとって、自らの技術が社会で活用されるという意識が芽生える瞬間があります。GAPファンドは、その最初の一歩を後押しする存在です。資金支援に加え、‟あなたの技術は社会に必要とされている”と伝えることで、最初の意思決定を後押しする役割があると感じています。これまでの採択プロジェクトには、医療・環境・情報通信など多様な分野のシーズが含まれており、いくつかは事業化に向けて次のステージに進みつつあります」
岡田氏「技術の優位性だけではなく、市場や社会における価値をどのように構築するかが問われるフェーズに、伴走者として寄り添える点が、このファンドの強みです。資金提供のみならず、事業開発や市場仮説の検証といった、創業前後の不確実性に対して、VC(ベンチャーキャピタル)ならではの知見とネットワークを活かし、さまざまな角度から支援を行っています」
岡田氏「最近は“GAPファンドという仕組みがあるから、やってみよう”と研究者側から手が上がるようにもなってきています。制度がうねりとなって広がっていることは実に素晴らしいと思います」
印象に残る採択プロジェクトとその成果
本学GAPファンドプログラムからは、多くの大学発スタートアップが誕生しました。GAPファンドから生まれた実績は、大学・VC・大企業による三者共創の可能性を体現した成果でもあり、また、成功事例が研究者のモチベーションを高め、研究室から社会に出る技術を目指す文化が広がりつつあることも、大きな成果のひとつといえそうです。

―数ある採択プログラムの中で、印象に残るプロジェクトは
下條氏「クレプシードラは独自の空間音響収録・再生技術、AI等を用いて音の到来や遠近感を表現する空間音響技術を提供する東京科学大学認定スタートアップ、また、digzymeはバイオインフォマテイクスによる酵素開発を行う東京科学大学認定スタートアップであり、技術的には非常に難解な領域ですが、両者とも研究開発から起業という道を選び、GAPファンドの意義を象徴する存在になっています」
岡田氏「彼らは、“起業したい”という強い意志をもって臨んでいた。その情熱に私たちも動かされました。GAPファンドという制度の存在だけでなく、起業家としての覚悟、実行力が相まって成果に結びついた好例です」
下條氏「他にもQuantum Zeroや雨宮先生、伊原先生のプロジェクトは量子センサやエネルギー関連など、当社既存事業との接点も見えるような先進的なテーマで非常に印象深いです。我々としても、採択プロジェクトは資金支援対象としてだけではなく、将来的な事業パートナーとして捉えています。技術領域や業界への親和性を見極めながら、将来的なパートナー候補および、新たな事業領域の発掘に向けて、社内でも積極的に共有しているんですよ」
- クレプシードラ株式会社「音響コンテンツの企画・研究開発」
- 株式会社digzyme「バイオインフォマテイクスによる革新的酵素の創出」
- 株式会社Quantum Zero 「ダイヤモンド量子センサの研究開発」
みらい創造インベストメンツの、支援ノウハウと実践知
スタートアップ支援の現場で、みらい創造インベストメンツが重視するのは、資金面だけではありません。その先にある「事業化のリアリティ」をどう創り出すか。これこそが、同社がGAPファンド運営に携わる大きな意義でもある、と岡田氏は語ります。

―みらい創造での、スタートアップの成長を支援するための取り組みについてお聞かせください
岡田氏「やはり、アカデミアの知と、我々の事業化ノウハウを掛け合わせることで、より良い社会実装につなげたい、という想いがあります。技術は確かに重要ですが、それを必要とする市場が存在しない限り、独りよがりな価値にとどまってしまいます。私たちVCは、市場を一緒に作る、というリスクをスタートアップとともに背負う覚悟で向き合っています。マーケット・経営・技術開発、この三本柱を同時に立ち上げる難しさに正面から向き合い、挑戦を支える。それが我々のスタイルです」
同社はGAPファンドの支援において、アントレプレナー・イン・レジデンス(EIR)を含む専門人材をプロジェクトごとにアサインし、技術と市場の適合性を検証する体制を構築。初期段階の研究シーズに対して、顧客視点を織り交ぜたピボット(軌道修正)を可能にする環境を整備しています。
芙蓉総合リースが提供する、成長支援のかたち
大企業として、実直かつ柔軟なアプローチでスタートアップに向き合う芙蓉総合リース。そこには、リース会社の枠を超えたあらたな企業価値の模索があります。同社は、近年、リース・ファイナンスという手段に加え、エクイティ投資やアライアンス先との共同事業にも取り組みを拡大しています。

―スタートアップと大企業がどのように連携し、成長を支援していくのか、その意義や仕組みを教えてください
下條氏「我々の立場はVCではないのですが、将来的な社会的価値や成長可能性を見て、スタートアップに関わることが増えています。大学発の技術は、初期のリスクが高いため、我々のようなプレーヤーが間に入って橋渡しすることが重要だと考えています。かつては、自社の事業領域に近いかどうかを軸に連携を考えていました。しかし今は、それだけでは見落としてしまう可能性の芽を、もっと積極的に探しにいく姿勢が求められていると感じます」
機器を貸す、から、「共に創る」という視点でスタートアップと向き合う姿勢は、実利にとどまらず、未来価値を重視する企業文化がもたらしているものではないか、と岡田氏は芙蓉総合リースの在り方を評価します。

岡田氏「事業会社が、自社ビジネスに直結しないテーマにも関心を持ってくださる、というのはとても貴重ですね。社会課題や未来の需要を見据え、今できることを一緒に模索できるようになったのは、まさに“進化”です。そこには、常にパートナーシップを大切にしてきた芙蓉総合リースだからこその、企業文化というものが礎としてあるのではないかと思います」
下條氏「そうかもしれません。私たちはリース会社として、事業リスクを取ってきました。スタートアップ支援においても、リスクを取ります。しかし、リースの延長線ではなく、新規事業の入口として接点を持つ。将来的なシナジーの芽を信じて、取り組んでいます」
ディープテックとの共創が切り拓く未来
近年注目されるディープテック領域には、明確な市場や事業収益がすぐには見えにくいテーマが多くあります。しかしながら、こうした先端技術にこそ共創の意義があり、企業・大学・スタートアップが三位一体となって挑む価値があるといえるようです。
―大学やINDESTのような場に求めることがあれば、お話しください
岡田氏「大学がもつプラットフォームの価値は、フラットさ。そして、企業の論理ではアクセスしづらいアイデアや研究に触れられる“場の力”にあります。このINDESTのような拠点は、技術シーズと企業ニーズの接点として、より高度な協働が可能になる空間ではないでしょうか」
下條氏「大学での交流から、我々が想定もしていなかったヒントを得られることがあります。そういった場から、新しい社会価値が生まれると信じています。事業創出の偶発性にこそ、可能性があると思います。我々が取り組むべきは、“まだ名前のない市場”にどうアクセスするか。そのためにこそ、大学・スタートアップ・企業の三者連携が不可欠だろうと思っています」
おわりに——“進化”と“共創”をたのしむ企業へ
本対談を通じて、GAPファンドという仕組みの本質が浮かび上がりました。それは、大学の知が社会と接続し、あらたな産業の芽を育てていく「共創の場」であるということ。そして、資金提供者も、事業会社も、支援者でありながら自身もそこに飛び込み、ともに進化していくプレーヤーであるべき、というメッセージです。
岡田氏「最終的には、関わる人々自身がたのしんでいるかどうか。変化の中に価値を見出し、社会に還元していけるか。それが、すべての出発点なのだと思います」
下條氏「事業のタネを見出し、仲間とともに形にしていく。そこに喜びがあるからこそ、組織も“進化”できるのだと思います」
GAPファンドプログラムは、資金供給としての役目を超え、研究者の視野を社会へと拡げながら、スタートアップを形づくるためのプラットフォームへと進化を遂げようとしているようです。東京科学大学で、GAPファンドから始まる知と企業のクロスオーバー。そこには、あらたなイノベーションの可能性が見えはじめています。

株式会社みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田 祐之 氏
東京工業大学大学院修士課程修了後、東京電力入社。原子力部門にて新技術開発に従事。独立系VCに出向し、ハンズオン支援を手掛ける。「大企業と中小企業」、「事業会社と金融」を理解し、事業組成からサービス化、営業戦略までの戦略立案と実行の経験を積む。2014年にみらい創造機構(現みらい創造インベストメンツ)を設立。みらい創造インベストメンツは、東京工業大学と連携協定を締結しているVCで、研究開発型スタートアップの創業前から起業後の事業拡大まで、技術の社会実装に伴走し、「みらいを創造する」活動を行っています。現在は、東京科学大学関連のベンチャーを中心に、研究開発型スタートアップへの投資に加え、創業前の技術シーズからの事業化にも注力。大学発新産業創出プログラムや、地域のスタートアップ・エコシステム共創プログラムにも複数採択され、研究者に伴走しながら、新たな産業の創出を推進しています。
芙蓉総合リース株式会社 常務執行役員 下條 剛史 氏
早稲田大学卒業後、富士銀行(現みずほ銀行)に入行。国内での法人営業を経て、1995年から2006年までニューヨークやシンガポール、シカゴ等の海外拠点での業務に従事。主に、日系企業への融資業務を通じ、日本企業の海外事業拡大に貢献。シカゴでは米国の金融子会社に出向し、最先端の金融商品を学ぶ。2006年に帰国後、不動産ファイナンスやシンジケーションローンを取扱う部署で不動産の流動化や、キャッシュフローファイナンスに従事。2010年から2018年までモスクワとミラノで拠点長として、拠点経営に携わり、日本と各駐在国の経済的交流、発展に貢献。2018年に芙蓉総合リースに入社し、主に鉄道会社、電力会社をはじめとする社会インフラ系企業や食品、生損保等の企業を顧客とする営業部の部長として、RM活動に従事。現在は、スタートアップ投資や産学連携、M&A、取引先様とのパートナーシップ等によって、国内外における芙蓉総合リースの新領域開拓を推進。
(テキスト・サムネイル CM・URA 小川由美子 /写真 堀川健一郎)