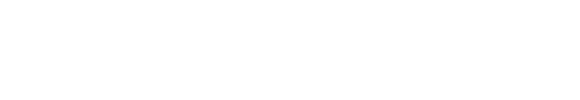イベント・ニュース EVENT / NEWS
2025年2月28日
【開催報告】Science Tokyo(東京科学大学)INDESTが拓く量子の未来シリーズ第1弾|「量子コンピュータの産業化」実現に向けた グローバルエコシステムの構築
日時2025年 2月20日(木)15:00~17:00
2月20日、Science Tokyo(東京科学大学)INDESTで、「Science Tokyo(東京科学大学)INDESTが拓く量子の未来」『量子コンピュータの産業化』実現に向けたグローバルエコシステムの構築」を開催しました。
国立研究開発法人産業技術総合研究所、量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)のセンター長であり、東京科学大学特別顧問 益一哉名誉教授、日本を代表する量子コンピュータスタートアップ株式会社Jij のCEO 山城悠氏を迎え、5つのテーマにもとづいて量子コンピュータの最新動向、今後の戦略について、量子コンピュータ最前線に立つそれぞれの立場から広く語っていただきました。
テーマ
- 世界で唯一無二の研究開発拠点」を目指す 産総研・G-QuATの取組とは?
- グローバルビジネスの最新動向と将来戦略
- 産官学連携による革新的なエコシステムの構築とは?
- グローバルでのユースケース創出に向けてできることとは?
- 日本の量子技術における強みとグローバルリーダーシップ確立への展望

本学イノベーションデザイン機構副機構長が司会をつとめ、冒頭ではINDESTの機能や取り組みについて紹介しました。2023年4月にオープンした本施設がコミュニティとして成長しながら、スタートアップエコシステムの拠点を目指すINDEST。2025年には、次世代技術のひとつとして注目される「量子」をテーマとした学びの場を拓き、世界を変えるスタートアップの創出、ディープテックスタートアップ支援につなげたいと抱負を述べました。本編では、山城氏がJij起ち上げの経緯や企業概要を説明、益氏からは「テーマ1」につなげて、産総研・G-CuATの取組についてお話しいただきました。
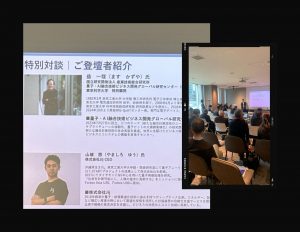
テーマ1:「世界で唯一無二の研究開発拠点」を目指す 産総研・G-QuATの取組とは?
益氏は、量子技術の領域を整理した上で、特に量子コンピュータに焦点を当て、各国が研究・産業・ビジョンに対して積極的に投資を行っている現状を概説。産総研・G-QuATでは、量子技術の研究開発を加速し、産業応用を視野に入れた拠点形成を目指していると説明しました。また、自らも研究開発を行う一方で、アカデミアや産業界を支える研究開発プラットフォームの役割を果たすことが使命、としました。
「世界で唯一無二の研究センター」を目指すために…
- 量子コンピュータの実用化に向けた基礎研究と応用開発(量子回路製造、システム化、サプライチェーン、計算基盤など)
- 機能や場所の提供、スタートアップ創出などの産業支援の推進
- 国内外のアカデミアや産業界とともにグローバルビジネスエコシステムの構築 など
テーマ2:量子技術の現状と展望
益氏は、量子業界はもはや研究機関だけのものではなく、産業界へと軸が移行している点を指摘しました。多くの組織が日常的に企業、政府機関、学術機関向けに自社商品や商用製品へのアクセスを提供している現状について、データを用いて説明しました。「昔はリニアモデルの時代。科学があり、技術があり、そこからビジネスに展開した。しかし、いまは同時進行の時代」「現在は、 科学も基礎科学においてもビジネス想定し、イノベーションまで同時進行で動いている」と、量子コンピュータの実用化に向けた現状と課題についても説き、量子アニーリングやゲート方式といった異なるアプローチの特徴や、エラー訂正技術の進展など多岐にわたるテーマを取り上げました。
山城氏は、「ビジネスのサイクルをそのまま研究に組み込んでいくことが、この分野の加速を生んでいる」と同意。量子コンピュータの分野では、基礎研究の段階でスタートアップと協力し、ユーザーに試してもらった結果を研究に直接フィードバックするループがすでに生まれていることにも触れ、基礎研究と実用化に向けた取り組みが同時に進行している、と量子技術の特徴を浮き彫りにしました。
テーマ3:産官学連携による革新的なエコシステムの構築とは?
量子技術の発展には、産業界、学術界、政府の協調や協力が不可欠であることを前提に、産総研のような組織とJijなどの民間企業がどのように連携し、新しいエコシステムを構築しているか議論されました。
山城氏は、「量子技術の分野では産官学連携が自然と生まれやすい環境が整っている」と述べました。日本には量子技術に関する研究拠点が多数あり、そこには大学だけでなく企業も参画し、Jijもそうした拠点に関わってアカデミアの研究者と議論を重ねているそうです。曰く、「量子技術は、ビジネスと研究の距離が必然的に近くなる領域であり、結果として産官学連携が自然に進んでいると感じる。例えば、弊社はJSTのSTARTプロジェクト発の企業で、JSTのイベントなどでも産学連携について議論する機会が多くある。一般的な産学連携では、アカデミアの技術をいかに産業に展開するかが課題となるが、量子分野ではすでに密接な関係が築かれており、エコシステムも機能している」。そのうえで、ハードウェア分野においては、量子技術の拠点となる「物理的な場所」の不足が課題であると指摘。そして、G-QuATの新施設がこの課題を解決する場となることへの期待を示し、「リアルな拠点の存在が、エコシステムのさらなる発展に不可欠」と強調すると、G-QuATがその役割を果たすことで、産官学連携の基盤がより強固になるとの見解を述べました。
益氏も「産総研の役割は単なる研究開発にとどまらず、日本の産業とアカデミアの基礎研究をさらに発展させることにある」と続け、量子技術の分野では、基礎研究とビジネスが一体となって動いているため、ビジネスの推進で基礎研究の課題も、より明確になる点を示し、「その橋渡し役として産業と研究の双方に貢献していきたい」と語り、「G-QuATは日本が世界と競争するための場であり、個々の利益だけではなく、日本全体の発展を目指す、そのためには、多様な人々が協力し合う環境をつくることが欠かせない」と語りました。

テーマ4:日本の量子技術における強みと課題
先端技術の分野で一定の成功を収めている日本が、グローバルなリーダーシップを果たすには何が必要か。量子技術においても、具体的なユースケースを創出し、国際市場での競争力を強化することが重要、として議論されました。
益氏は、経済複雑性指標を用いて日本の産業基盤の強さを示しながら、量子コンピュータに必要な部材開発や統合技術においても強みを持つ可能性を言明。「世界的に見ても、日本は新たな高度なハードウェアを作る集積地になれる」として、さらには日本産業界のユースケース開発への関心が高く、グローバルに見ても特異な位置にあることを述べました。
山城氏は、自社のイギリス進出についても言及し、グローバルを巻き込む重要性を示しました。合わせて、量子コンピュータには希釈冷凍機や制御装置、光学系など多くの高度な技術が求められるが、日本はこれらの部材供給においても優れた技術を持ち、世界的にも注目を集めている、とつなぎました。「量子コンピューティングのユースケースにおいて、日本は特に注目されています。例えば、Q-STARのような産業団体に日本では企業が多数参加しています。実際のアプリケーション開発が進んでいる点でも優位性があります」として、光の波長制御やノイズ低減に関する技術は日本の得意分野として、海外の企業も日本の部材を活用している、と挙げ、量子コンピュータの分野でリーダーシップを発揮するには、技術開発にとどまらず、実際のユースケースを創出することが必要、と繰り返しました。
また、G-QuATのようなテストベッドが本分野の発展を後押しすることについての期待を受けた益氏は「日本全体を良くしたいという思いで取り組んでいる。それはG-QuATとしても常に意識し、発信し続けるべきことだ」と唱えました。
テーマ5:日本の量子技術における強みとグローバルリーダーシップ確立への展望
日本は高い技術力と製造基盤を有し、特に量子コンピュータのハードウェア技術において強みを発揮しています。日本の量子技術の優位性と、グローバルリーダーシップ確立に向けた展望について、両氏から一言ずつコメントをいただきました。
益氏は「できない理由を挙げるのではなく、できる方法を考えよう」と強調し、「結局は志とやる気が大事。みなさん、一緒に取り組みましょう」と呼びかけました。
山城氏は、「日本のユースケースをうまく輸出して、世界の量子コンピュータ上で動くソフトウェアのリーダーシップを確立するところまで、実現したい」と対談を締めくくりました。

おしまいに
今回の特別対談では、量子コンピュータの最前線と産業化に向けた課題について活発な議論が交わされました。G-QuATが果たすべき役割、産学官の連携の重要性、多様な研究者が集うエコシステムの構築に至るまで、多岐にわたるテーマが取り上げられました。基礎研究から応用、ビジネスまでをつなげることで多様な人材が集まり、新たな価値が創出される。研究の多様性を活かし、共通言語を持たない者同士が協力しながら新たな価値を生み出すダイナミズムーーその「楽しさ」こそが、エコシステムを発展させる鍵となるかもしれません。
Q&Aセッションでは、高校生からの質問に対し、益氏と山城氏が「興味を持ち続けることの大切さ」を説き、若い世代の挑戦を後押しする場面もありました。その言葉は、未来へのエールとして響きました。

対談後の山城悠氏、益一哉氏
本イベントには、INDEST単独イベント史上最多となる300名を超える方々にご登録いただき、量子コンピュータへの関心の高さがうかがえました。ご参加いただいた皆さま、そして、本イベントに関心を寄せてくださったみなさまに、心より感謝申し上げます。また、登壇者のおふたり、お力添えくださった関係者のみなさまにも、深くお礼をお申し上げます。
INDESTは「世界を変える大学発スタートアップを育てる」拠点として、引き続きイノベーション創出を支援してまいります。