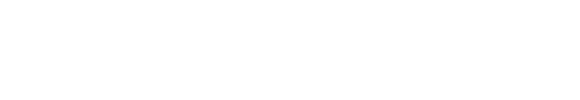イベント・ニュース EVENT / NEWS
2025年7月2日
【開催報告】Science Tokyo Startup Night2025①
日時2025年 6月26日(木)16:00-21:00
東京科学大学イノベーションデザイン機構は、2024年6月26日(木)虎ノ門ヒルズCIC Tokyoで、Venture Café Tokyoとの共催イベント「Science Tokyo Startup Night2025 」を開催しました。
本イベントは、大学発“テック”スタートアップの創出を加速させるべく、研究者・スタートアップ関係者・投資家・行政など、多様なステークホルダーが一堂に会し、最新の戦略や実践知を共有する特別な場。今年度は、東京科学大学のかかげる「ビジョナリーイニシアティブ(VI)」に焦点をあて、国内外のディープテックスタートアップの潮流や、大学の役割・進化について、さまざまな議論が交わされました。本報告では、当日のセッションの模様を三部にわけてお届けします。
目次
Science Tokyo Startup Night2025①|オープニング/基調講演/ディープテック女性起業家セッション
Science Tokyo Startup Night2025②|インタビューセッション/オープンディスカッション/閉会
Science Tokyo Startup Night2025③|社会変革チャレンジ賞2025授賞式
①16:00 – 16:05
Opening:Science Tokyo Startup Night
~Science Tokyo Startup Night 2025~世界を変える、大学発“テック”スタートアップ
大学発“テック”スタートアップの創出を推進する東京科学大学。開会にあたり、主催である東京科学大学から田中学長が登壇し、本イベントの趣旨説明を行いました。大学発のディープテックスタートアップの創出を核とした取り組みの全体像を紹介するとともに、「社会に開かれた大学」としての姿勢と、今日のような多様なステークホルダーが交わる場の意義を改めて強調しました。
「研究者、スタートアップ関係者、投資家といった多様な方々が集う貴重な場。これからの各セッションを通じ、視点の異なる者同士が理解を深め、新たな発見や連携の種が芽吹くことを期待しています」

(東京科学大学 学長 田中 雄二郎)
②16:05 – 16:25
Opening Session|東京科学大学のVI戦略と、世界を変えるディープテックスタートアップの創成戦略
「善き未来」の実現をビジョンに掲げる東京科学大学では、社会変革を目指す研究体制「ビジョナリーイニシアティブ(VI)」を通して、研究分野・研究ステージの枠を越えた融合研究とその社会実装を推進しています。
オープニングセッションでは、東京科学大学が掲げる「ビジョナリーイニシアティブ(VI)」を中心とした研究・起業戦略を紹介。東京科学大学 大竹理事長、MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー村上由美子氏が登壇、CIC名倉智之氏がモデレーターをつとめました。本セッションでは、従来の共同研究にとどまらない、産業界と連携したスタートアップ創出の戦略などをテーマに、市場の変化に俊敏に対応するための大学改革、それに対する投資家の視点や期待についても掘り下げ、大学の戦略を、市場を知る投資家から見た際にどう評価できるか、その期待値や課題を述べました。
VIによる研究・起業の変革
大竹理事長は、基礎研究から社会実装までを一貫して推進するVIの構想について紹介しました。
「University 4.0のエコシステムを動かすには、社会実装までを視野に入れたビジョン共有が不可欠です。グローバルな連携を前提に、国内外のアカデミアや産業界とともに、新しいスタートアップのあり方を切り拓いていきたい」と述べ、従来の研究体制を超えた越境的な連携や、アントレプレナーシップ教育の重要性にも言及。「ロールモデルとなる」先導的な人材の育成と、若手研究者との接点強化がエコシステム形成の鍵になると語りました。
投資家から見た大学の可能性
村上氏は、国内外の大学発スタートアップに対する投資実績をもとに、大学が果たすべき人材供給機能と、日本のエコシステムがまさに「音を立てて変化しつつある」今、その兆しについて指摘。リスクマネーの流通や、長期視点での資金提供(グラント)の文化は不可欠であり、大学こそがその基盤となるべきと述べました。
「スタンフォードやハーバードは、エコシステムの中核に人材供給機能を持っています。日本もいま、優秀な学生が起業や海外スタートアップを志す動きが出てきており、20年前のアメリカのような変化が起きつつあります」
起業家精神を育む大学へ
名倉氏との対話を通じ、大学が起業家精神を育む「文化」と「環境」づくりに取り組む必要性も共有され、「あらゆる分野の学生が起業家精神に触れられるような大学の文化と仕掛けが必要」「東京科学大学がエコシステムの起点となり、次世代のイノベーションビルダーを育てたい」などといった言葉も交わされました。また、起業家人材の輩出だけでなく、彼らを支える資金・文化・制度の土壌を大学がどう築いていくかが重要であるという点で一致。日本発のディープテックスタートアップ創出に向けた展望を語りました。

(東京科学大学 理事長 大竹尚登/MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー 村上由美子氏/モデレーター:東京科学大学特任教授・CIC東京ゼネラルマネージャー 名倉 勝氏)
③16:35 – 16:55
基調講演
「未来を切り拓くディープテック─社会実装に向けたルール形成の最前線」
世界を変えるディープテックには、ゲームチェンジャーとなることが期待されます。ディープテックが世界に変革をもたらすには、その技術力だけでなく、あらたなルール形成を見据えた戦略も不可欠です。
本セッションでは、ディープテックの社会実装における「ルール形成」に焦点を当て、官民連携による国際標準化の最前線について、経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室長 池田 陽子氏にご講演いただきました。ここでは、先ず、筑波大学発ベンチャー・サイバーダイン社のHAL(サイボーグ型医療支援ロボット)を例に、技術が先行するディープテックにおいて「ルールが存在しない」という現実に直面した経験を紹介いただきました。サイバーダインは、自らが国際規格を主導的に策定する「ルールメーカー」となり、技術の社会実装に向けた国際ルール形成に挑んだといいます。こうした事例をふまえ、日本政府が取り組むスタートアップ支援5ヵ年計画の全体像や、近年注目を集める「規制のサンドボックス制度」の運用についても解説しました。池田氏は「エコシステムを生む“エコシステム”を創ることが重要」と述べ、ディープテックにおける起業や事業化に向けた環境整備の必要性を語りました。

(経済産業省 経済産業政策局 競争環境整備室長 池田 陽子氏)
④17:05 – 18:10
対談&スタートアップピッチ
ディープテック女性起業家セッション
急成長が期待されるディープテック領域において、女性起業家の活躍も注目されています。本セッションには、MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー 村上 由美子 氏、 株式会社tayo 執行役員/WISER統括 土井 ゆりか 氏が登壇。本学 真尾 淑子特任教授をモデレーターに、女性起業家支援の専門家から現状の課題、今後の展望、そして、社会に寄せる期待について語っていただきました。
ベンチャーキャピタルの立場として、村上氏は、日本の女性の教育水準は世界トップクラスである一方、女性創業者に対する投資は全体の2%に過ぎない、という現実を紹介。そのギャップに「投資機会」としての可能性を見出し、女性起業家を対象としたファンドを立ち上げた背景を語りました。一方、女性研究者の支援に取り組む土井氏は、自身の体験を通して、研究現場における女性の孤立感やロールモデルの不足といった課題に着目。女性研究者200名以上が参加するコミュニティ運営や、若手女性を対象としたGAPファンドの実施など、起業と研究の接続点を生み出す取り組みを紹介しました。
両氏は、イノベーション創出には多様な視点が不可欠であり、「女性だから」ではなく、女性もいる環境が当たり前になることの重要性を訴えました。登壇者の言葉からは、「ディープテック領域における女性のプレゼンスを高めるクリティカルマスの必要性」と、次世代に向けた着実な変化の兆しが感じられる、力強いセッションとなりました。

(MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー 村上 由美子 氏/ 株式会社tayo 執行役員/WISER統括 土井 ゆりか 氏/モデレーター:東京科学大学 特任教授 真尾 淑子)
⑤17:40-18:15
社会課題に挑む女性起業家たちが登壇──女性起業家ピッチセッション開催
女性起業家ピッチセッションでは、5名の登壇者がそれぞれの取り組みを発表。医療やバイオ、テクノロジーの分野で、革新的な事業に挑む女性起業家によるプレゼンが行われました。
ゲストピッチ:ファーメンステーション 酒井里奈氏
オープニングでは、株式会社ファーメンステーション代表の酒井里奈氏が登壇。未利用バイオマスを活用し、発酵技術によって機能性バイオ素材を開発する独自のビジネスモデルを紹介しました。岩手県の自社工場を拠点に、原料開発から製品化までを一貫して担い、食品・医療分野への展開を進めています。女性起業家としての挑戦や、スケールする企業としての志も語られました。
刑部祐里子氏(東京科学大学 教授)
刑部教授は、国産ゲノム編集技術「TiD」による希少疾患の治療アプローチを紹介。既存技術に比べてオフターゲットが少なく、安全性と編集効率に優れた「TiDx」を活用し、DMD(デュシェンヌ型筋ジストロフィー)などへの応用を目指す。現在、非臨床試験に向けて準備を進めており、製薬企業との協業体制構築にも取り組んでいると述べました。
丸山智香氏(株式会社Dhwincycle)
丸山氏は、歯科衛生士不足という社会課題に対し、AIを活用した育成支援アプリ「テレシカ」を開発。教育の質を均一化し、定着支援と業務効率化を両立することで、地域医療の底上げを狙います。4ヶ月間の実証では相談件数の減少や検査件数の向上など、顕著な成果を示しました。
金子奏絵氏(株式会社フィルダクト)
フィルダクト代表の金子氏は、3D技術とAIを活用した歯科矯正技術を紹介。従来より高額な矯正治療を、手の届く価格帯で提供し、4000人以上にサービスを展開中。すでに130以上の歯科医院と連携し、歯科技工士の離職率が高い現状への課題意識からスタートした事業として説明しました。
大塚響子氏(HerLifeLab株式会社)
「心」に寄り添い、「身体」を科学する、を掲げるHerLifeLab。代表の大塚氏は、更年期障害に特化したオンライン診療サービスを発表。本サービスでは、データに基づいたパーソナライズドケアで、ホルモン療法、栄養指導、心理サポートをワンストップで提供。高い治療継続率と高単価モデルの実績を紹介しました。
コメンテーター総括
ピッチ終了後には、株式会社Fleurinaryブランスクム文葉氏と、東京大学エッジキャピタルパートナーズ 塩原梓氏が総評を行いました。
各登壇者の発表について、専門性の高さと社会課題への鋭いアプローチ、そしてビジネスとしての実行可能性などに着目。特に、医療・ライフサイエンス領域における研究と実装の橋渡し、現場課題を捉えた着眼点の独自性、収益モデルや市場展開戦略の明確さなどが主要なコメントポイントとなりました。技術の優位性だけでなく、実用化・事業化に向けたチームビルディングや協業体制の構築、将来的なグローバル展開の視野、そしてユーザー視点に立脚した製品・サービス設計の重要性も指摘され、今後の成長に向けた期待が寄せられました。

メインステージ後半の様子は、STSN開催報告②よりご覧いただけます。
(テキスト・サムネイル URA 小川由美子)